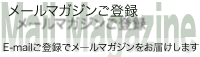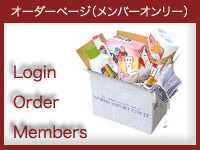ITALY 
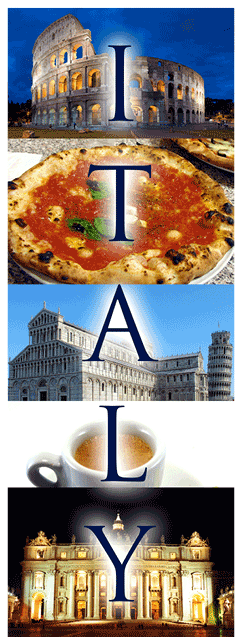 北イタリア
北イタリア
アルプスの山麓に広がる街「トリノ」、モードの発信地「ミラノ」、そして水の都「ヴェネチア」などがあります。ミラノからヴェネチアの間に広がるピアヌーラ・パダーナと呼ばれる大平原(ポー川流域)には、「ピアチェンツァ」「クレモナ」「マントヴァ」、ロミオとジュリエットの町として知られる「ヴェローナ」など小さな町々が点在しています。
 ドイツ・スイス国境に近い北イタリアの食文化は、アルプス山麓で育つ牛を使った料理やさまざまな伝統チーズが有名です。ヴェネチアなど海に面している街ならば、地中海の魚料理も見逃せません。銘酒バローロやバルバレスコ、良質な白ワインやスプマンテなど、エレガントなイタリアワインが楽しめます。また、ポー川流域はお米の一大産地でもあり、リゾットも北イタリアでポピュラーな料理のひとつです。
ドイツ・スイス国境に近い北イタリアの食文化は、アルプス山麓で育つ牛を使った料理やさまざまな伝統チーズが有名です。ヴェネチアなど海に面している街ならば、地中海の魚料理も見逃せません。銘酒バローロやバルバレスコ、良質な白ワインやスプマンテなど、エレガントなイタリアワインが楽しめます。また、ポー川流域はお米の一大産地でもあり、リゾットも北イタリアでポピュラーな料理のひとつです。
中部イタリア
ルネッサンス発祥の地花の都「フィレンツェ」をはじめ、「シエナ」「サン・ジミニャーノ」「ピエンツァ」「アレッツォ」「ピサ」など、中世の面影を残した可愛らしい小さな町々があります。フィレンツェを州都とするトスカーナ州は、その美しい田園風景でも知られたところ。なだらかな丘にブドウ畑やオリーブ畑が連なり、まるで絵画のような風景だそうです。また、海沿いには「ジェノバ」を州都とするリグリア州。「チンクエ・テッレ」や「ポルト・フィーノ」などヨーロッパの上流階級が集まるリゾート地があります。世界最古の大学がある「ボローニャ」を州都とするエミリア・ロマーニャ州には、パルミッジャーノ・レッジャーノや生ハムの産地「パルマ」やバルサミコ酢の「モデナ」などもあります。
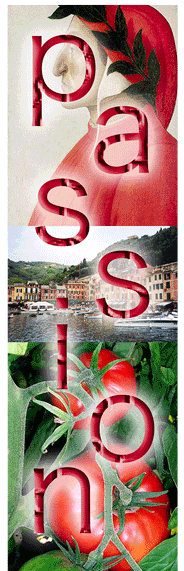 食文化は、トスカーナ州やエミリア・ロマーニャ州では、豚肉のサラミや生ハムが有名です。パルミッジャーノ・レッジャーノチーズをはじめとするチーズも豊富。海沿いの町なら、やはり地中海産の魚介料理も楽しめます。ジェノバのバジリコを使ったジェノベーゼソース(イタリアでは「アル・ペスト」と呼ぶ)、ボローニャのボロネーゼソース(ミートソースのこと)などおなじみのパスタ料理も。トスカーナでは「ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ(フィレンツェ風Tボーンステーキ)」も郷土料理として親しまれています。
食文化は、トスカーナ州やエミリア・ロマーニャ州では、豚肉のサラミや生ハムが有名です。パルミッジャーノ・レッジャーノチーズをはじめとするチーズも豊富。海沿いの町なら、やはり地中海産の魚介料理も楽しめます。ジェノバのバジリコを使ったジェノベーゼソース(イタリアでは「アル・ペスト」と呼ぶ)、ボローニャのボロネーゼソース(ミートソースのこと)などおなじみのパスタ料理も。トスカーナでは「ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ(フィレンツェ風Tボーンステーキ)」も郷土料理として親しまれています。
ローマ
古代ローマ帝国の首都でもあったローマには、「フォロ・ロマーノ」「コロッセオ」「パンテオン」など、2000年の歴史を今に伝える偉大な遺跡群が街の中心に残っています。また、キリスト教の総本山バチカン市国もローマ市内。世界最大の教会「サン・ピエトロ大聖堂」やミケランジェロの天井画が有名な「システィーナ礼拝堂」やラファエッロの名画がいくつも見られる「バチカン美術館」は、ローマ観光の目玉です。「ローマの休日」で知られる「スペイン階段」「真実の口」「トレヴィの泉」なども有名ですよね。絵画ファン、建築ファン、歴史ファンの誰もがまずは訪れたい「永遠の都」です。
ローマ料理の歴史は大変古いのですが、特に18、19世紀の「庶民」料理が今のローマ料理のもとになっています。その頃、ローマの人々は特に牧畜を営んでいたため、豚肉、羊肉、牛肉、また富裕者は食べなかった内臓物を中心とする、エネルギーの元になる料理が主流です。たとえばローズマリーとジャガイモを添えて調理した子羊肉のオーブン焼「アヴァッキオ」、子牛のソテー「ローマ風サルティンボッカ」、「カルチョーフィ(アーティチョーク)のローマ風」などの個性豊かな伝統料理があります。また、飢えと寒さをしのぐのに最適な、風味豊かで味のしっかりしたソースを使ったパスタ料理は力の元となる料理のひとつ。トマトソースと豚のほお肉を使ったソースや、日本でもポピュラーな「カルボナーラ」は、ローマの郷土パスタです。スパゲッティ・カルボナーラを日本語訳すると、炭焼きスパゲティになります。この料理は、ローマ周辺の森林で炭焼きを営んでいた人たちの主な料理でした。肉体的に大変な仕事で、卵、ベーコン、羊乳のペコリーノチーズを使ったしっかりした料理が必要だったのです。日本で馴染みのあるカルボナーラは生クリームが使われていますが、本場では卵とチーズだけのソースで作られます。生クリームを使用するカルボナーラは日本風にアレンジしたものなのだそうです。さらに、イタリアのピッツァにはナポリ風ピッツァとローマ風ピッツァ2種類が主流で、モチモチのナポリ風とは対照的に、ローマ風の特徴は平たくカリッとした生地のピッツァなのだそうです。
南部イタリア
「ナポリを見て死ね」といわれるほど風光明媚なナポリや、地中海文明の十字路として3千年もの歴史を持つシチリア島など、南部イタリアの見どころは豊富です。ギリシャ時代に植民地として「マグナ・グレチア(大ギリシャ)」と呼ばれた歴史もあり、ギリシャ神殿などの遺跡群も各地で見られます。イタリア半島をブーツに見立てると、ちょうどかかとの部分にあたるプーリア州には、不思議な形をした集落「アルベロベッロ」や洞窟住居「マテーラ」のほか、真白い町「オストゥーニ」など、建築学的にも興味深い小さな町が点在しています。シチリア島内にも、アラブ・ノルマン様式の教会がエキゾチックな州都「パレルモ」や、ギリシャ神殿遺跡のある「アグリジェント」、塩田のある「トラパニ」、リゾート地として有名な「タオルミーナ」など、個性的な町々がぎっしりと詰まっています。
地中海に囲まれたイタリア半島、特に南部の食文化は、近海で取れる魚介類を使った料理が有名です。マグロやイワシ、タコ、ウニなどの地中海ならではの濃厚な風味が楽しめます。また、小麦粉の産地でもある南イタリアでは、パスタ料理の美味しさも群を抜いています。
「ニューシネマパラダイス」や「グランブルー」など、シチリアを舞台にしたイタリア映画も多い。
南部・シチリア島
シチリアは、イタリアの南端に浮かぶ島で、イタリア半島をブーツに例えると、そのブーツがコンッと蹴った小石のような場所にあります。濃い青空はいつも晴れ渡り、からりと乾燥した空気にレモンの花が揺れ、島をぐるりと囲む透明な地中海がもたらす新鮮な魚介類。南イタリアを代表するこの島は、島全体が「シチリア州」として、イタリア20州のうちのひとつに数えられてはいますが、この土地にはイタリアとは少し違った独特の雰囲気を持つ文化が流れています。地図を見ると、シチリア島は見事に地中海のど真ん中に浮かんでいるのがわかります。ギリシャ、アフリカ、アラブ諸国も目と鼻の先。その地理的条件から、この島はさまざまな民族の通り道となってきました。最初の侵入者は、古代ギリシャ人。ローマ帝国時代よりもっと古い時代です。そして、ローマ帝国、ビザンチン帝国、ノルマン王国、スペイン王国、フランス王国…。この島は、その時代の強国に侵略・支配されて、その折々に各民族の文化が持ち込まれました。シラクーサやアグリジェントに残るギリシャ遺跡をはじめ、州都パレルモに見るアラブ・ノルマン様式のエキゾチックな教会群、スペイン支配時代に建築されたシチリア・バロック様式の壮麗な街並み。ギリシャ、ローマ、アラブ、アフリカ、スペインなどの地中海文化が融合して、現在のシチリアができあがっているため、イタリアよりもっと広い地中海世界の記憶を留めており、それゆえに「この島には、地中海三千年分の歴史がある」といわれているのです。
そしてその記憶の凝縮は、建築物などのハード面だけでなく、伝統や食、芸術など、ソフト面でも存分に感じることができます。古代ギリシャ神話に起源をもつ収穫祭や、アラブ式の伝統マグロ漁。太陽の恩恵を受けた島の豊富な食材と長い歴史の掛け合わせが生む食卓はとても豊か。日本人顔負けの魚介料理に、名産のアーモンドやピスタチオが使われるパスタ料理、アフリカ料理の「クスクス」までシチリアバージョンになって伝統料理に登場します。
イタリア小話
〜トマトは悪魔の実!?〜
イタリアといえば真っ赤なトマト料理が思い浮かびますが、実はこのトマト、以前は長い間、その鮮やかな赤い色から「毒がある悪魔の実」と考えられ、忌み嫌われていたというから驚きです。トマトの原産地は南米アンデス山脈の高地で、厳しい気候でも育つ生命力の強い植物。その名はアステカ語で「膨らむ果実」を意味する「トマトゥル」に由来します。大航海時代にヨーロッパに渡ったトマトですが、当初は観賞用とされ、毒草だと誤解されていたため、食べる人はいませんでした。ところが17世紀、イタリアのナポリ地方が深刻な飢饉に見舞われ、飢えをしのぐために意を決してトマトは食べられました。初めて食べたときには、きっとその甘さとみずみずしさに驚いたことでしょう。こうして、「悪魔の実」という不名誉な称号を返上し、個性豊かな食材として認められたトマトは、ナポリを発信地にヨーロッパ各地に広がり、食卓に欠かせないものとなりました。今では、トマトはイタリア語でポモドロ=「黄金のリンゴ」と呼ばれているほどです。ポピュラーなスパゲッティ・ポモドロは、イタリアのおふくろの味なのだそうです。
また、トマトの赤にはリコピンという栄養素が含まれており、動脈硬化など様々な生活習慣病の原因となる活性酸素を抑えるといわれています。ヨーロッパでは、「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがあるほどです。
〜統治政策から生まれたピザ〜
日本でも人気の「ピザ・マルゲリータ」は、イタリアの国王とその王妃マルゲリータがナポリを訪れた時、緑色のバジル、白のモツァレラチーズ、そして赤のトマトでイタリアの国旗をイメージし誕生し、王妃の名前が付けられました。そんなナポリのピザは、もちもちっとした生地と香ばしい焼き色が特徴で、日本のレストランで食べると1枚1000円前後はするほどのごちそうです。しかし実は歴史的にみると、ピッツァとナポリの関係には思わぬ背景がありました。ナポリは1502年から約2世紀スペインの、その後、イタリア統一の1861年まで150年間フランス系のブルボン王朝の支配下にありました。支配者達は、怠け者のナポリの人達を支配するのにかなり苦労したそうです。なにせ彼らは「その日に食べる物さえあれば、あとは遊んでいた方が良い!」という考えだったのです。どの時代も不変だったナポリ湾の美しい風景や壮大な山々を眺めれば、そんな気持ちになるのも分かる気がします。そこで執政者達はナポリ統治方法に「3F政策」を取ったと言われています。3つのFとは小麦粉(Farina),祭(Festa),絞首刑台(Forca)の頭文字です。民衆に適当な小麦粉を与えて餓えを凌がせ、たまに祭りをさせて適当に喜ばせ、必要なら絞首刑台に送って権力者の恐ろしさを示す。というものでした。この「3F政策」は、ナポリの民衆の心理をよくつかんだ政治政策でした。 ピッツァはこの「3F政策」から生まれた食べ物です。それは、もちろん今の様にバリエーションはなく、小麦粉を練って上にトマトを載せてオリーブオイルをかけて焼いたものでした。ちなみにトマトを上に乗せて焼いたものは、トマトが南米のペルーからもたらされた16世紀末以降、17世紀位からと考えられるので、その前はよりシンプルだったわけです。 しかし、これさえ食べていればナポリの人達は満腹感と栄養が保証されていました。「無秩序が秩序になっていた街、ナポリ」その街を統治できた3要素のうちのひとつが、ピッツァの始まりだなんて、なんだか不思議な感じですがナポリの人々に親近感がわいてきます。「その日に食べる物さえあれば、あとは遊んでいた方が良い!」この考えで生きていれば、きっとどんな餓えだろうと貧乏だろうと、楽しんでしまえることでしょう。イタリアの陽気な明るさの原点と原動力が垣間見られる歴史だと思いませんか?
 その後ピッツァは、ナポリの人々の暮らしに溶け込み、トマトの登場等によって形を変えながら、人気の高い庶民の食べ物となりました。 そして、美味しくて合理的で栄養価が高いなど、様々な魅力と共に1960年代以降イタリア全土にピッツァブームが起こり、世界中にも広まって行ったのです。
その後ピッツァは、ナポリの人々の暮らしに溶け込み、トマトの登場等によって形を変えながら、人気の高い庶民の食べ物となりました。 そして、美味しくて合理的で栄養価が高いなど、様々な魅力と共に1960年代以降イタリア全土にピッツァブームが起こり、世界中にも広まって行ったのです。
このように形を変えながら、広まってゆくナポリの伝統ピッツァ、「ナポリ・ピッツァの伝統技術を守らなくては!」と危機感を感じたのがナポリのピッツァ職人達だったのでしょう。ナポリでは1984年に「Associazione vera pizza napoletana」(真のナポリピッツァ協会)が設立されています。古くから伝わるピッツァ職人の伝統技術が世代交代を経ても受け継がれるよう、ナポリ市をあげてピッツァの伝統的な製法を守ろうと尽力しているそうです。ピッツァ職人(ピッツェリア)は協会の定めるいくつかの条件をクリアするとナポリピッツァのお店として認定されます。条件は、(1)生地の材料は小麦粉、酵母、塩、水だけ(2)生地は手を使って延ばす(3)焼き方は窯の床面でじか焼き(4)窯の燃料は薪か木くず(5)仕上がりがふっくらしていて縁が盛り上がっているなどです。協会のトレードマークは、仮面をつけたナポリの道化師『プルチネッラ』がヴェスビオ火山を背景に真剣にピッツァを焼いている姿。 日本にも認定を受けたお店がいくつかあるようで、横浜にも店の入り口に協会のマークを見かけるようになりました。日本にピザ文化が入って来た当初は、アメリカ経由で入ってきたため、ナポリピッツァとは程遠い物でした。そういえば思い起こしてみると、私が子供の頃に食べていた馴染みのピザといえば、サラミやピーマン、コーンなど色とりどりに具がのっているパンみたいなカリカリ冷凍ピザ。大人になってイタリアンレストランで本格窯焼きのナポリピッツアを食べたときは、生地のもちもちさと焦げ目の香ばしさ、縁までおいしい味わいに、「これがピッツアなるものか!」と感激したものです。
ナポリのピッツア屋さんでは、やはり「マリナーラ」と「マルゲリータ」が人気のようで、それしかメニューにない店もあるそうです。「マリナーラ」が登場したのは1750年頃、トマトを使った最初のピッツァです。名前から魚介が使われていると思いきや、生地にトマトソース・オリーブオイル・オレガノのみのとてもシンプルなピッツアで、忙しい漁師がパン屋に作らせて手軽に空腹を満たしたのがその名の由来だそうです。そして「マルゲリータ」は、1889年に初めて作られ、こちらも生地にトマトソース・バジリコ・モッツアレラと、とてもシンプルなピッツア。イタリア王国の第二代国王ウンベルト1世の王妃マルゲリータ の好物だったため、彼女の名前が付いたのだそうです。目にも鮮やかなイタリアンカラーとあって、イタリアでも常に人気No1だそうです。
私はイタリアに行ったことはありませんが、テレビや雑誌で見る情報でとっても明るい陽気なイメージがあります。その明るさは、自分の生まれた土地をこよなく愛し、侵略によって入ってくる異文化も受け入れる寛容さが感じられ、そしてどんなことも、やり始めたら楽しんだ方がいい、とりあえず今この瞬間を思いっきり楽しんで暮らす「なるようになるさ」の精神が息づいている国のように感じました。最近、3年間沖縄で暮らしていた友人と、人間関係について話しました。「沖縄の人たちは、すごく人なつっこくてとても気持ちいい!東京の人たちの多くは、何となく個々で壁を作って接している感じで、どこかさめている。」と言っていました。もちろんその土地に住む全員がそうとは限りませんが、その環境が人間を形成することに大きく影響していることは違いないなあと感じました。子ども〜親〜親戚〜近隣〜学校・会社〜地域環境〜国〜世界、環境は波紋のように広がって途絶えることはありません。今回イタリア特集をしていて、ナポリ人の「その日に食べる物さえあれば、あとは遊んでいた方が良い!」という生き方が、とても自然で気持ちいい!と思うところでした。