 aroma
aroma
においを感じるしくみ
嗅覚は、五感のなかでもっとも原始的で本能に直結した感覚といわれています。人がにおいを嗅ぐと、その分子は鼻のなかの嗅細胞にキャッチされ、大脳辺縁系に伝わり、まず安全なにおいかどうかが判断されます。これは動物と同じで、私たち人間も嗅ぎなれないにおいを嗅ぐと、それを不快なにおいと見なして警戒心を抱きます。食べ物の腐っているかどうかの見分けも、見た目とにおいが重要な判断になりますものね。このように嗅覚は、生命を守るために危険回避の役割を担った感覚なのです。
また、大脳辺縁系は情動、欲動、記憶などをコントロールしているので、嗅覚は記憶ともっとも結びつきやすい感覚でもあります。そして、生まれたときに一番発達している五感がこの嗅覚なので、生まれたばかりの赤ちゃんは、まだ目がよく見えなくてもお母さんのにおいをしっかりと記憶します。過去に嗅ぎなれたにおいを久しぶりに嗅ぐと、当時の懐かしい記憶が呼び覚まされるのも、嗅覚と記憶が密接な関係にあるからです。さらに、においの善し悪しの判断も、においにまつわる記憶に左右されています。例えば、赤ちゃんは大便のニオイを不快に思うことはありません。周りの大人たちが「クサイ」と顔をしかめるのを見て、「大便はクサイ」という学習をするのです。ほかにも、好きな食べ物ならにおいを嗅いだだけで食欲がわくし、嫌いな食べ物はにおいを嗅ぐのも嫌だと思うでしょう。最初は好きだったのに、具合の悪いときに食べて吐いた、食べ過ぎて気持ちが悪くなったなどの経験から嫌いになると、においすら受けつけなくなるということもあります。他の人が嫌がるにおいでも、良い記憶と結びついている人にとっては好きなにおいになるし、その逆の場合もあります。『くさや』や『ドリアン』などにおいのきつい食べ物も、子どもの頃からにおいをかいでいて当たり前のように食卓に出て親がおいしいといいながら食べている環境に育ったなら、きっと良い記憶のにおいなのでしょうね。私は大人になって出会ったにおいだったので、どうしても「臭い」記憶のものと似たにおいを連想してしまって苦手なのです...。そんな人間の嗅覚には、ふたつの大きな特徴があります。
ひとつは、順応(疲労)しやすいことです。最初は気になったどんなにおいでも、素早く慣れてそのうち気にならなくなります。もうひとつは、個人差が大きいことです。人種、性別、年齢、鍛錬の度合いなどによって、においの感じ方はそれぞれ異なります。同じ強さのにおいでも、感じる人・感じない人、不快な人・不快でない人がいることもよくあります。性別でいうと、一般に男性よりも女性のほうが比較的においに敏感だそうです。
日本人の香り文化
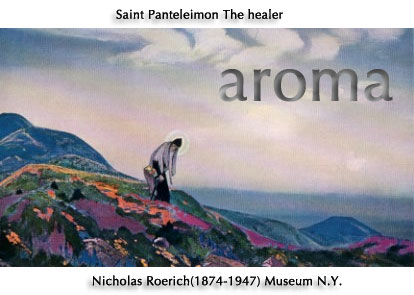 世界的にみて日本人は、においに敏感な国民だといわれています。その大きな理由のひとつとして、欧米人に比べてほとんど体臭が感じられないということが挙げられます。ワキガや体臭に悩む日本人は多数いますが、欧米人はあまり悩みません。というのも、民族(人種)別でワキガ体質の割合は大きく異なり、一般的に黒人は100%ワキガ体質で、欧米人は80%であるといわれています。体臭はあって当たり前なので、当たり前のことで悩んだりはしないのです。これに対し、日本人は約10%、中国人は3〜5%がワキガ体質であるとされています。それは低脂肪高繊維質、植物性食品が中心の食生活と多いに関係があったようです。動物性脂肪の酸化がにおいの発生源となりやすいことがわかっているからです。パーセンテージが低いからこそ、においの強さは逆に目立つのです。体臭があまりないゆえに、日本人は比較的弱いにおいでも敏感にキャッチできる嗅覚の繊細さを持ち合わせているといえます。体臭の強さに慣れている欧米人は、日本人の多くにとって強いと感じるにおいでも、それほど強くは感じないのではないでしょうか。
世界的にみて日本人は、においに敏感な国民だといわれています。その大きな理由のひとつとして、欧米人に比べてほとんど体臭が感じられないということが挙げられます。ワキガや体臭に悩む日本人は多数いますが、欧米人はあまり悩みません。というのも、民族(人種)別でワキガ体質の割合は大きく異なり、一般的に黒人は100%ワキガ体質で、欧米人は80%であるといわれています。体臭はあって当たり前なので、当たり前のことで悩んだりはしないのです。これに対し、日本人は約10%、中国人は3〜5%がワキガ体質であるとされています。それは低脂肪高繊維質、植物性食品が中心の食生活と多いに関係があったようです。動物性脂肪の酸化がにおいの発生源となりやすいことがわかっているからです。パーセンテージが低いからこそ、においの強さは逆に目立つのです。体臭があまりないゆえに、日本人は比較的弱いにおいでも敏感にキャッチできる嗅覚の繊細さを持ち合わせているといえます。体臭の強さに慣れている欧米人は、日本人の多くにとって強いと感じるにおいでも、それほど強くは感じないのではないでしょうか。
そんな日本人の繊細な嗅覚を物語るものの一つが、お香の文化です。お香の歴史は古く、日本へは仏教と一緒にその使い方が伝わりました。ですから、奈良時代までは宗教との結びつきが強く、邪気を払い仏前を清めるための「供香(そなえこう)」として、お香がたかれていたようです。当時のお香は今のような線香ではなく、香りのする木を炊いたり、いろいろな香料の粉末を炭の粉や梅肉などと一緒に練り合わせて熟成させた丸薬状のメ練香モを使ったりしていました。平安時代になると、貴族たちの間では宗教的な意味合いだけではなく、香りを楽しむためにたかれるようになり、香を焚くのが日常となるまでに発展しました。衣服に香りをたき込む「移り香(うつりが)」、部屋でお香をたく「空薫(そらだき)」といった言葉が生まれたのもこの頃。香りで暮しを演出をするという優雅な習慣が生まれました。また、平安貴族たちは、独自の練香を作ることにかなりの情熱を注いでいたようで、「薫物合」(たきものあわせ)という、自分独自の練香を作ってはその優劣を競い合う遊びもしていたといいます。平安貴族たちの作った自分だけの香りは、自分の象徴でもあり存在感をアピールするものであったようです。当時、現代のように結婚した男女が同居するという習慣がなく、夫が妻の家へ通う
(通い婚)が常でした。月や星、ロウソクの明かりしかない闇夜の中、逢瀬を重ねる夫の存在を、着物に焚きこめた練香によって判断していたそうです。視覚よりも嗅覚に頼っている部分がかなり大きかったのです。そういえば、『源氏物語』の中でもこのようなシーンは頻繁に出てきたことを思い出しました。
このように、お香が平安貴族に大流行した理由としては、香りを楽しんだり存在をアピールすることだけでなく、当時は入浴がままならず、不快な体臭を消すためにお香をしきりに焚いていたという話は有名です。また、心を落ち着けたりするような手段としても大活躍していたようです。十二単衣にお香をたきしめたり、香料を細かく刻んで入れた匂い袋を肌に身につけたり、引き出し付きの箱型の枕の中に香炉を入れて香をたいて寝る「香枕」は、安眠を誘うとして大流行しました。そして江戸時代には線香が登場して手軽に香りを楽しめるようになり、庶民の間でも香りの文化が花開きました。気分をすっきりさせたいとき、落ち着かせたいとき、人をもてなすとき、そしてときには防臭や消臭、医療といった実益のためにあらゆる香料を調合し、香りのある暮らしを送ってきました。
そして現在でも日本の伝統として、お花やお茶ほどポピュラーではありませんが、「香道」という芸道もあります。これは、香りを鑑賞するもので、そのための香道具もいろいろ製作されました。このように精神文化として発展してきた香りと日本人との関係には、なかなか奥深いものがあります。ちなみに、西洋の香水が上陸したのは、明治時代の欧米文化の到来からで、当時は芸者を中心に日本庶民の間にも浸透していったそうです。
 海外の香り文化
海外の香り文化
香りの歴史は古く、BC3000年頃始まった、古代エジプトにまでさかのぼります。
一説には、火を使うことによって生じる煙から、初めて人間は “香り” を得たと言われています。「香り」を表す「Perfume」(パフューム)はラテン語の「Per Fumum」(煙によって立ち昇る)が語源であることからも頷けるところがあります。火によって生じる煙が香りとともに天に昇っていく様子に、神と通じるものを感じたのでしょうか、古代エジプトでは、香料は神聖で悪を排除し、悪から身を守るものとされ、神への供物の防腐目的であったり、ミイラを作る時の防腐剤、など宗教的な目的に多く利用されていたようです。また、香りの持つ神秘的な力は、特権階級の人々の間では、権威を表す小道具のひとつとして、そしてまた人を魅了する美容の目的でも用いられていました。香油は娯楽用としても使われ、強い陽射しから肌を守ったり、肌をやわらかくするために使われました。当時の原料は100%天然素材のはちみつや乳香、ミルクなどで、かなり高価なものでした。
中世ヨーロッパでは、香りを楽しむ(=香水をつける)習慣が、庶民の間へ広く普及しました。当時は現代のようにお風呂に入る習慣がなかったため、香水の用途はおしゃれというよりも、体臭を消すという実用的な目的が強かったようです。また現代のアロマテラピーのように病を治すという医学的な目的でも使われていました。1370年には現代の香水の基盤となる”アルコールに香料を溶かす製法”が、初めてハンガリーで確立しました。女王エリザベスのために作られたのです。香水が“香り”史上、初めて処方された瞬間でした。
18世紀になると、人々は毎日香りを変えて楽しむほど、香水が一般的なものとなりました。かのフランス女王マリー・アントワネットは、特注のフローラルな香りの香水を身に付けていたため、外出中も常にその所在がわかったとと伝えられています。また、ナポレオン・ボナパルトは政治家、軍事家としてだけでなく、大の香水ファンとしても有名です。彼が好んで付けた香水は、現代のオーデ・コロンのような比較的軽い香りのものだったようです。
無臭こそ清潔!? 消臭文化の危険性
最近、頻繁にコマーシャルで目にするようになった『除菌消臭』グッズ。90年代から抗菌グッズの爆発的ブームが訪れ、日本人の清潔指向は一気に強まってきました。これは、私たちの周りから生活臭がどんどん少なくなっていることからはじまっているようです。例えば下水道の発達で水洗トイレが普及されたこと、気密性の高い近代的な住宅増加により各家庭のにおいは外に漏れていかなくなったこと、自然が少なくなったことによる土ぼこりや草むらのにおいがしなくなったこと、などがあげられ、近代化=消臭化になっているかのようです。菌は肉眼では見えませんが、においは鼻がしっかりキャッチするので、「不快なにおい=不潔」という共通認識ができあがっていくのです。
こうして身の回りのにおいが消されると、当然人間のにおいそのものが目立ちはじめます。いくら日本人の体臭が少ないとはいえ、周りが無臭なので、自分たちの体のにおいにまで敏感になっていきます。ニンニク、ギョウザ、納豆などのにおいの強い食品は無臭化され、無煙ロースターの焼き肉店が人気を呼び、食事のあとには必ずニオイ消しを口に含みます。夏場の制汗剤はもはや手放せません。平安時代の香り文化は、いまや消臭文化にとって代わったようです。
そんな「においがなくて当たり前の時代」に生まれ育った現代の若者の間で、『体臭恐怖』という病気が発生しています。これは、自分の体臭を極端に気にするあまり対人関係に支障をきたす病気で、対人恐怖の一種です。対人恐怖とは日本人独特の病気で、海外では病名そのものが存在しません。何につけても「平均」「横並び」を良しとする日本的な発想が、この病気を発生させているようです。平均からはみ出せば目立ちますが、目立つことを「悪」とみなすところから、「自分が周りからどう見られているか? 自分は変だと思われていないか?」というこだわりが強くなり、他人の視線や態度、存在そのものまで怖れるようになること、これが対人恐怖です。
どんな生き物でも、生きているからこそのにおいがあって当たり前です。においが記憶と深く結びついているからこそ、私たちの取り巻くすべてのものとつながって受け入れていければ、そのものの持つにおいさえも尊重したくなるはずです。『見えない・聞こえない・しゃべれない』の三重苦を乗り超えたヘレン・ケラーは、 こんな言葉を残しています。「大人には人格を表すにおいがあり、赤ちゃんにはそのにおいがない。大人でもその人らしい独自のにおいのない人は、活気がなく面白みがない」。彼女は肉体的なハンデならではの敏感な嗅覚の持ち主でした。においはかけがえのないものであり、彼女は人の放つにおいから、その人の性格やライフスタイルまで、見事に言い当てたと言います。欧米人が香水を愛用しているのも、実は体臭を引き立てるためのものでもあるようです。実際香水は肌に直接つけるものですから、その人の体温や体質によって微妙に香りを変化させます。体臭は1人ひとり違うものですから、自分のにおいを最も魅力的に引き出してくれる香水も千差万別です。つまり、欧米では体臭も立派な「個性」として、アピールすべき魅力のひとつなのです。以前ニューヨークに滞在したことのあるサークルスタッフから聞いた話ですが、ニューヨークのレストランに入ると実にいろんなにおいが混じっていて何ともいえない空間なのだそうです。食事のにおい、香水のきついにおい、そして干し草のような酸っぱい汗のにおい...。でも、そんなにおいのする空間が、とらわれがなくみんながちゃんと主張し合っていて好きだったそうです。欧米の人はよく肉の腐ったにおいがするといいますが、欧米の人からしてみれば日本人は魚臭いともいわれていたみたいです。そしてインド人はやっぱりカレー臭い。みんな、その国の生活文化がにおいになっていて、個性的ですばらしいことだと思いませんか?そう考えると、日本の無臭消臭文化は何てむなしいんだろうと思ってしまいます。
サークルの商品でも、ダウニーやバウンスの洗剤類や、アロマキャンドルやドロワライナーなどのルームフレグランス、様々な欧米のすてきな香り文化をご紹介しています。自分の体臭や自宅の生活臭と合わさって、その人なりのすてきな香りを演出してくれるアイテムです。これからも、世界のいろいろな香り文化を皆さんにご紹介できればと思っています。平安時代のおしゃれや自己主張のための香りを、いつまでも受け継いでいきたいものですね。




